
婫姧僗僇僀僗億乕僣 亙WINTER亜 僀僇儘僗弌斉

旘峴婡偺僾儘偑儂乕儉價儖僪偺
婡懱傪僛儘偐傜嶌傞丅
偦偟偰丄慡崙傪旘傃夞傟傞婡懱偵偟偨偄丅
僷僀儘僢僩傕偄傞丄
媄弍幰傕偄傞丅
僒億乕僩偡傞恖払傕偄傞丅
偟偐偟丄偦傟偼墦偔尟偟偄摴偺傝側偺偩丅
旘峴婡偺僾儘偑傛偭偰偨偐偭偰
彫偝側寉旘峴婡傪嶌傝偼偠傔偨
 丂埨懞壚擵偝傫偼丄嶰旽廳岺偺僥僗僩僷僀儘僢僩偩丅帺塹戉偱愴摤婡僷僀儘僢僩傪柋傔偨偁偲柉娫偵堏傝丄尰嵼偼導塩柤屆壆嬻峘偵椬愙偡傞嶰旽廳岺
嬈噴柤屆壆峲嬻塅拡僔僗僥儉惢嶌強彫杚撿岺応偱杊塹挕偵堷偒搉偝傟傞愴摤婡側偳偺帋尡旘峴傗怴宆婡偺奐敪側偳傪峴偭偰偄傞丅
丂埨懞壚擵偝傫偼丄嶰旽廳岺偺僥僗僩僷僀儘僢僩偩丅帺塹戉偱愴摤婡僷僀儘僢僩傪柋傔偨偁偲柉娫偵堏傝丄尰嵼偼導塩柤屆壆嬻峘偵椬愙偡傞嶰旽廳岺
嬈噴柤屆壆峲嬻塅拡僔僗僥儉惢嶌強彫杚撿岺応偱杊塹挕偵堷偒搉偝傟傞愴摤婡側偳偺帋尡旘峴傗怴宆婡偺奐敪側偳傪峴偭偰偄傞丅乽僷僀儘僢僩偵側傞偙偲丄偦偟偰帺暘偱嶌偭偨旘峴婡傪旘偽偡偙偲偑柌偱偡乿偲偄偆嵟弶偺柌偼丄尒帠偵幚尰偱偒偨丅偟偐偟帺暘偱嶌偭偨旘峴婡傪旘 偽偡偲偄偆偺偼偦偆娙扨偱偼側偄丅嶰旽廳岺偼擔杮傪戙昞偡傞峲嬻婡惢憿儊乕僇乕偱偁傞偲偼偄偊丄僥僗僩僷僀儘僢僩偺埨懞偝傫偵傕旘峴婡傪嶌傜偣 偰偔傟傞傢偗偱偼側偄丅
丂偲偙傠偑偁傞擔丄椬導偺奺柋尨巗偱乽奆偱旘峴婡傪庤嶌傝偟偰旘偽偦偆乿偲偄偆寁夋偺儊儞僶乕傪曞廤偟偰偄傞偙偲傪抦偭偨丅彫杚偐傜奺柋尨傑偱 偼幵偱侾帪娫偲偐偐傜側偄嫍棧偵偁傞丅偦偙偱僥僗僩僷僀儘僢僩偺愭攜偱偁傝忋巌偱傕偁傞搉绯媑擵偝傫乮俥亅俀巟墖愴摤婡偺弶旘峴傪柋傔偨乯偲傕 桿偄崌傢偣偰丄嶲壛偡傞偙偲偵偟偨偺偱偁傞丅
 丂偙偺寁夋偼丄傕偲傕偲偼乮幮乯拞晹峲嬻塅拡媄弍僙儞僞乕乮摉帪偼乮幮乯拞晹塅拡嶻嬈壢妛媄弍怳嫽僙儞僞乕偲拞晹峲嬻嶻嬈媄弍怳嫽嫤媍夛乯偑棫
埬偟偨傕偺偩偭偨丅拞晹抧曽偵偼愳嶈廳岺傗嶰旽廳岺丄偦偟偰晉巑廳岺側偳擔杮傪戙昞偡傞峲嬻塅拡嶻嬈偺嫆揰偑悢懡偔偁傝丄摨僙儞僞乕偼拞晹抧曽
偵偍偗傞峲嬻塅拡嶻嬈偺偝傜側傞敪揥傗怳嫽偺偨傔偺偝傑偞傑側妶摦傪揥奐偟偰偄傞丅偦偺堦娐偲偟偰堦斒偺恖偑婥寉偵嶲壛偟偰旘峴婡偺偙偲傪妛傋
傞妶摦傪揥奐偟傛偆偲偄偆偙偲偵側偭偨丅
丂偙偺寁夋偼丄傕偲傕偲偼乮幮乯拞晹峲嬻塅拡媄弍僙儞僞乕乮摉帪偼乮幮乯拞晹塅拡嶻嬈壢妛媄弍怳嫽僙儞僞乕偲拞晹峲嬻嶻嬈媄弍怳嫽嫤媍夛乯偑棫
埬偟偨傕偺偩偭偨丅拞晹抧曽偵偼愳嶈廳岺傗嶰旽廳岺丄偦偟偰晉巑廳岺側偳擔杮傪戙昞偡傞峲嬻塅拡嶻嬈偺嫆揰偑悢懡偔偁傝丄摨僙儞僞乕偼拞晹抧曽
偵偍偗傞峲嬻塅拡嶻嬈偺偝傜側傞敪揥傗怳嫽偺偨傔偺偝傑偞傑側妶摦傪揥奐偟偰偄傞丅偦偺堦娐偲偟偰堦斒偺恖偑婥寉偵嶲壛偟偰旘峴婡偺偙偲傪妛傋
傞妶摦傪揥奐偟傛偆偲偄偆偙偲偵側偭偨丅嬶懱揑偵偼愳嶈廳岺偐傜摨僙儞僞乕偵弌岦偟偰偄偨桍悾尦徍偝傫偑壒摢傪偲傝丄傾儊儕僇偐傜彫宆婡偺僉僢僩僾儗乕儞傪峸擖丅偙傟傪奺柋尨巗偵婑憽偟丄偐偐傒偑偼傜峲嬻塅拡攷暔娰乮尰嵼偼偐偐傒偑偼傜峲嬻塅拡壢妛攷暔娰偵夵徧乯偺廋暅岺朳傗岺嶌婡夿側偳傪巊偭偰乽儂乕儉價儖僩婡惢嶌懱尡嫵幒乿傪奐嵜偡傞偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅
乽摉弶廤傑偭偨偺偼60悢柤丅嬃偄偨偙偲偵丄偦偺栺俉妱偼愳嶈廳岺傗嶰旽廳岺偺尰栶傗俷俛丄偄傢偽旘峴婡嶌傝偺僾儘偨偪偩偭偨偺偱偡乿偲桍悾偝傫丅
丂晛抜偐傜帪戙偺嵟愭抂傪偄偔僴僀僥僋峲嬻婡傪嶌偭偰偄傞恖偨偪偑丄偳偆偟偰彫偝側旘峴婡傪庤嶌傝偟偨偄偲巚偭偨偺偩傠偆丅
乽峲嬻婡惢憿儊乕僇乕偱偼僗僞僢僼傕崅搙偵暘嬈壔偟偰偍傝丄偦傟偧傟偑扴摉偡傞偺偼峲嬻婡偺偛偔尷傜傟偨晹暘偵偡偓傑偣傫丅帺暘偼旘峴婡傪嶌偭 偰偄傞偺偩偲偄偆幚姶偼丄側偐側偐摼傜傟側偄偐傕偟傟傑偣傫偹丅偟偐偟彫偝側寉旘峴婡側傜偽丄偡傋偰傪帺暘偨偪偺庤偱嶌傞偙偲偑偱偒丄傂傚偭偲 偟偨傜帺暘偨偪偺庤偱旘偽偡偙偲傕偱偒傞丅傕偲傕偲旘峴婡偑岲偒偱偙偺摴偵恑傫偩恖偨偪偱偡偐傜丄偦傟偼偲偰傕枺椡揑側偙偲側偺偱偡乿
梊嶼晄懌偱寁夋偼拞抐偟偨偑
俶俹俷愝棫偱幏擮偺姰惉傪傔偞偡
 丂惢嶌婡偲偟偰慖偽傟偨俼倁亅俇俙偼丄傾儊儕僇偺僶儞僘丒僄傾僋儔僼僩幮偑惢憿丒斕攧偡傞僉僢僩僾儗乕儞偩丅摨幮偼扨嵗偺俼倁亅俁偐傜係嵗偺俼
倁亅10傑偱偝傑偞傑側儂乕儉價儖僩婡傪儔僀儞僫僢僾偟偰偄傞偑丄奺柋尨偵嬤偄拞擔杮峲嬻愱栧妛峑偱傕暋嵗偺俼倁亅係傪惂嶌偟偨幚愌偑偁偭偨丅
丂惢嶌婡偲偟偰慖偽傟偨俼倁亅俇俙偼丄傾儊儕僇偺僶儞僘丒僄傾僋儔僼僩幮偑惢憿丒斕攧偡傞僉僢僩僾儗乕儞偩丅摨幮偼扨嵗偺俼倁亅俁偐傜係嵗偺俼
倁亅10傑偱偝傑偞傑側儂乕儉價儖僩婡傪儔僀儞僫僢僾偟偰偄傞偑丄奺柋尨偵嬤偄拞擔杮峲嬻愱栧妛峑偱傕暋嵗偺俼倁亅係傪惂嶌偟偨幚愌偑偁偭偨丅乽岞揑婡娭偑庡摫偡傞傕偺偱偡偐傜丄夦偟偘側傕偺傪嶌傞傢偗偵偼偄偒傑偣傫丅偟偐偟拞擔杮峲嬻愱栧妛峑偱惢嶌傪巜摫偟偨嶳嶈擡愭惗傕亀偙偺婡懱 側傜偽戝忎晇偩傠偆亁偲懢屰敾傪墴偟偰偔偩偝偄傑偟偨丅偨偩偟俼倁亅係偺傛偆側僞儞僨儉乮捈楍乯暋嵗傛傝偼僒僀僪僶僀僒僀僪乮暲楍乯暋嵗偺曽偑 惍旛惈傗憖廲惾偺巊偄堈偝偺柺偐傜傛偐傠偆偲偄偆偙偲偱丄俼倁亅俇俙傪慖傫偩偺偱偡乿
丂俼倁亅俇偼傾儊儕僇偱偼侾侽侽侽婡埲忋偑斕攧偝傟偰偄傞儀僗僩僙儔乕婡偱丄姰惉偡傟偽僙僗僫傗僷僀僷乕側偳偲偄偭偨戝庤儊乕僇乕惢偺寉旘峴婡 偵傂偗傪偲傜側偄嬥懏婡偱偁傞丅旜椫幃偺俼倁亅俇偲慜椫幃偺俼倁亅俇俙偲偑偁傞偑丄慖偽傟偨偺偼抧忋偱偺偲傝傑傢偟偺梕堈側俼倁亅俇俙偩偭偨丅
丂惢嶌偑僗僞乕僩偟偨偺偼俀侽侽侽擭12寧丅枅廡侾乣俀夞乮搚丄擔梛擔乯偺儁乕僗偱廤傑偭偰偼惢嶌傪恑傔丄傢偢偐俀擭傎偳偱僄儞僕儞傗寁婍椶傪偺 偧偔婡懱庡梫晹暘傪傎傏姰惉偝偣傞偙偲偑偱偒偨丅僉僢僩偲偼偄偊偐側傝夣挷側儁乕僗偱嶌嬈偑恑傫偩偺偼丄傗偼傝偝傑偞傑側乽僸僐乕僉偺僾儘乿偑 廤傑偭偰偄偨偨傔偩傠偆丅側偵偟傠儕儀僢僩傂偲偮傪懪偮偵偟偰傕丄惓妋偵丄僈僞側偔丄偟偐傕旤偟偔巇忋偘傞偵偼憡摉偺孭楙傪昁梫偲偡傞丅偙傫側 偲偒偵儊儞僶乕傪巜摫偱偒傞僾儘偑偄傞偺偼怱嫮偄偟丄昁梫側愱栧抦幆傗媄擻傪帩偭偨夛幮偺摨椈傗俷俛偵偝傜偵惡傪偐偗傞偙偲傕偱偒傞丅
 丂僥僗僩僷僀儘僢僩偲偟偰偼堦棳偩偑旘峴婡嶌傝偱偼慺恖偺搉绯偝傫傗埨懞偝傫傕
丂僥僗僩僷僀儘僢僩偲偟偰偼堦棳偩偑旘峴婡嶌傝偱偼慺恖偺搉绯偝傫傗埨懞偝傫傕乽偄偪偍偆嶰旽偺恖娫偲偟偰抪偢偐偟偔側偄傛偆偵偲丄儕儀僢僩偺懪偪曽傗岺嬶偺巊偄曽偵偮偄偰丄岺応偺愱栧壠偐傜慜傕偭偰巜摫傪庴偗偰偐傜嶲壛偟傑偟偨乮徫乯乿
偲偄偆偑丄惢憿僾儘偺慜偱偼晅偗從偒恘傕捠梡偟側偐偭偨偙偲偩傠偆丅懱尡嫵幒偱偼夵傔偰奺帺偺僗僉儖偵墳偠偨孭楙偲儗儀儖暘偗偑側偝傟丄悢恖扨埵偺僌儖乕僾偵暘偗偰巇帠偑傢傝傆傜傟偨丅
乽帺暘偱嬯楯偟偰傒偰丄儕儀僢僩偺侾杮侾杮偵嵃偑偙傕偭偰偄傞傫偩偲幚姶偟傑偟偨丅偦偆偟偰嵃傪偙傔偨儕儀僢僩偑丄師偵棃偨偲偒偵偼僾儘偺庤偱 懪偪捈偝傟偰偟傑偭偰僈僢僋儕偒偨偙偲傕傛偔偁傝傑偟偨偗偳乮徫乯丅偱傕丄偙傫側偵妝偟偄偙偲傪傗傔傞傢偗偵偼偄偐側偄乿偲搉绯偝傫丅
丂偲偙傠偑俀侽侽俁擭搙偵側偭偰丄偙偺寁夋偼撢嵙偟偰偟傑偆丅彅斒偺帠忣偐傜捛壛偺梊嶼偑擣傔傜傟偢丄僄儞僕儞傗寁婍側偳傪挷払偡傞儊僪偑棫偨 側偔側偭偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅惢嶌偵娭傢偭偨儊儞僶乕偼丄側傫偲偐惢嶌傪懕峴偱偒側偄偐偲峫偊偨偑丄拞屆僄儞僕儞傪挷払偡傞偩偗偱傕栺俀侽侽枩 墌傕偺旓梡偑偐偐傞丅柍棟傪偡傟偽儊儞僶乕偺摢妱傝偱晧扴偡傞偙偲傕壜擻偐傕偟傟側偄偑丄偦傟偱偼峀偔巗柉偺庤偱旘峴婡傪庤嶌傝偟偰傒傛偆偲偄 偆摉弶偺棟擮偑敄傟偰偟傑偆丅
丂偦偙偱儊儞僶乕偺恖偨偪偼峴惌傗懠偺朄恖偵棅傞偙偲側偔帺庡揑偵塣塩偑偱偒傞傛偆偵丄俶俹俷朄恖乮摿掕旕塩棙妶摦朄恖乯傪愝棫偟偰妶摦傪堷偒 宲偖偙偲偵偟偨丅偙偆偟偰俀侽侽俆擭俈寧偵愝棫偝傟偨偺偑俶俹俷朄恖乽俵俙俠俫 俛仌俥乿偱偁傞丅
乽俵俙俠俫乿偼壒懍偺儅僢僴偲摨偠僗儁儖偩偑丄儘乕儅帤偱乽傒傫側偱丄偁偮傑偭偰丄偪偭偪傖側丄傂偙偆偒乿偲彂偄偨偲偒偺摢暥帤偵傕側偭偰偄傞丅 乽俛仌俥乿偼乽價儖僪仌僼儔僀乿偺摢暥帤偩丅偮傑傝乽奆偱廤傑偭偰彫偝側旘峴婡傪嶌偭偰旘偽偦偆乿偲偄偆堄枴偵側傞丅幚嵺偵偼懠偵傕怓乆側堄枴 偑偁傞偦偆偩偑丄梫偡傞偵偦偆偄偆柤慜偱偁傞丅
柌偼擔杮慡崙傪旘傃傑傢傞偙偲
幚尰偱偒側偄棟桼偼側偄偼偢偩
 丂俶俹俷朄恖傪愝棫偟偨偐傜偲偄偭偰丄偦傟偱偳偙偐偐傜偍嬥偑揮偑傝崬傫偱偔傞傢偗偱偼側偄丅偨偩偟妶摦偺僼傿乕儖僪偼丄廬棃傛傝傕奿抜偲峀偑
偭偨丅
丂俶俹俷朄恖傪愝棫偟偨偐傜偲偄偭偰丄偦傟偱偳偙偐偐傜偍嬥偑揮偑傝崬傫偱偔傞傢偗偱偼側偄丅偨偩偟妶摦偺僼傿乕儖僪偼丄廬棃傛傝傕奿抜偲峀偑
偭偨丅乽偁偔傑偱儂乕儖價儖僩婡偺惢嶌傪妀偵偟側偑傜丄惵彮擭傪娷傓暆峀偄恖偨偪傪懳徾偲偡傞島墘夛傗僀儀儞僩側偳丄傛傝峀偔峲嬻僗億乕僣暥壔偺晛媦 傗孾敪偵娭傢傞妶摦傪揥奐偟偰偄偒偨偄偲峫偊偰偄傑偡乿偲俶俹俷朄恖棟帠挿偵廇擟偟偨嶅払楴偝傫丅
愳嶈廳岺偺弌恎偱丄儃乕僀儞僌俈俇俈傗俈俈俈偺嫟摨奐敪帠嬈偺偨傔偵傾儊儕僇偵挀嵼偟偰偄偨偙偲傕偁傞偲偄偆丄傗偼傝旘峴婡偺僾儘偱偁傞丅
丂偙偆偟偰傒傞偲愝寁丒惢憿丒旘峴偺僾儘偑廤傑偭偨乽俵俙俠俫 俛仌俥乿偼嫮傒傪敪婗偡傞丅峲嬻嫵幒傪奐嵜偡傞偵傕島巘偵偼帠寚偐側偄偟丄僾儘 偺僷僀儘僢僩偵傛傞憖廲嫵幒偩偭偰奐偗傞丅幚婡傪巊偭偰偺孭楙偼側偐側偐傓偢偐偟偄偑丄偡偱偵俁柺偺僨傿僗僾儗僀傪旛偊偨乽旘峴嫵堢梡僼儔僀僩 僔儈儏儗乕僞乕乿傕梡堄偝傟偰偍傝丄懡偔偺恖偵旘峴婡傪憖廲偡傞妝偟偝傪懱尡偟偰傕傜偍偆偲偄偆弨旛傕惍偊傜傟偰偄傞丅偙偺僼儔僀僩僔儈儏儗乕 僞乕偼巗斕僷僜僐儞偲俥俽俀侽侽係乮Microsoft幮惢乯傪儀乕僗偵偟偨傕偺偩偐傜丄僴乕僪僂僃傾偩偗側傜偽屄恖偺庯枴偱偦傠偊傜傟傞儗儀儖偩偲偼 偄偊傞偑丄儊乕僇乕偺尰栶僥僗僩僷僀儘僢僩偑巜摫偟偰偔傟傞偲偟偨傜丄偙傟偼枺椡揑偱偁傞丅
 丂偙偆偟偨妶摦傪捠偠偰乽俵俙俠俫丂俛仌俥乿偵懳偡傞棟夝偲昡壙偑崅傑傟偽丄偄偢傟偼婡懱晹昳側偳傪挷払偡傞偨傔偺曗彆嬥傗僗億儞僒乕偑偮偔偙
偲傕婜懸偱偒傞丅偩偑丄偨偲偊帒嬥揑側儊僪偑偮偄偨偲偟偰傕丄杮摉偺擄栤偼偦偺偁偲偵峊偊偰偄傞丅旘峴婡偑姰惉偟偰傕丄偦傟傪旘偽偡偨傔偵偼峲
嬻嬊偺嫋壜傪摼側偗傟偽側傜側偄偺偩丅
丂偙偆偟偨妶摦傪捠偠偰乽俵俙俠俫丂俛仌俥乿偵懳偡傞棟夝偲昡壙偑崅傑傟偽丄偄偢傟偼婡懱晹昳側偳傪挷払偡傞偨傔偺曗彆嬥傗僗億儞僒乕偑偮偔偙
偲傕婜懸偱偒傞丅偩偑丄偨偲偊帒嬥揑側儊僪偑偮偄偨偲偟偰傕丄杮摉偺擄栤偼偦偺偁偲偵峊偊偰偄傞丅旘峴婡偑姰惉偟偰傕丄偦傟傪旘偽偡偨傔偵偼峲
嬻嬊偺嫋壜傪摼側偗傟偽側傜側偄偺偩丅旘峴婡偼懴嬻徹柧偑側偗傟偽旘偽偡偙偲偼偱偒側偄乮峲嬻朄戞11忦乯偑丄懴嬻徹柧傪庢傞偨傔偵偼乮傕偪傠傫懴嬻徹柧偑側偄偆偪偐傜乯帋尡旘峴摍傪 峴偆昁梫偵側傞丅偦偙偱懴嬻徹柧偺側偄旘峴婡偱傕崙搚岎捠戝恇偺嫋壜傪庴偗傟偽旘偽偡偙偲偑偱偒傞偲偄偆婯掕偑偁傞丅偦傟偑乽峲嬻朄戞11忦偨偩 偟彂偒乿偩丅
儂乕儉價儖僩婡側偳懴嬻徹柧偑側偄婡懱傪旘峴偝偣傞偨傔偵偼丄偙偺偨偩偟彂偒偵偐偐傢傞彂椶怰嵏傗専嵏側偳傪僷僗偟丄抧忋妸憱丄僕儍儞僾旘峴偲 抜奒揑側旘峴帋尡傪姰椆偟偰弶傔偰堦斒揑側旘峴偑嫋壜偝傟傞丅偙偺婡懱偱傕偙偙傑偱偺旘峴偼壜擻偩偑丄懠偺儅僀僋儘儔僀僩婡側偳偲摨條偵丄偣偄 偤偄旘峴応偺応廃宱楬偺斖埻偺旘峴偟偐嫋壜偝傟側偄壜擻惈偑崅偄丅
乽偟偐偟巹偨偪偼丄偙偺婡懱偱擔杮拞傪旘傫偱傒偨偄偲巚偭偰偄傞偺偱偡乿偲埨懞偝傫丅
晛捠側傜偽丄偲偰傕柍棟偩丅
乽偳偆偟偰柍棟側偺偱偡偐乿
 丂懴嬻徹柧偺拞偵僄僋僗儁儕儊儞僞儖偲偄偆僇僥僑儕乕偺偁傞傾儊儕僇側傜偽丄儂乕儉價儖僩婡偱傕僋儘僗僇儞僩儕乕旘峴傪娷傔偐側傝偺帺桼搙偱嬻傪旘傇偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丄擔杮偵偼傾儊儕僇偺傛偆側僄僋僗儁儕儊儞僞儖丒僇僥僑儕乕偼側偔丄儂乕儉價儖僩婡傪旘峴偝偣傞応崌偼丄巊梡旘峴応丄
旘峴崅搙丄旘峴斖埻側偳偐側傝嵶偐偔惂栺偝傟偨忋偱偺傒嫋壜偝傟傞丅偙傟偼丄抧忋傗旘峴偺埨慡偵廫暘攝椂偟偨寢壥偩偲峫偊傜傟傞偑丄尒曽傪曄偊
傞偲丄愴屻擔杮偺帺嶌峲嬻婡暥壔偑朢偟偔惢嶌傕傎偲傫偳峴傢傟側偐偭偨偨傔丄傾儊儕僇偺傛偆側僇僥僑儕乕偑惗傑傟偰偔傞娐嫬偑堢偭偰偙側偐偭偨
偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂懴嬻徹柧偺拞偵僄僋僗儁儕儊儞僞儖偲偄偆僇僥僑儕乕偺偁傞傾儊儕僇側傜偽丄儂乕儉價儖僩婡偱傕僋儘僗僇儞僩儕乕旘峴傪娷傔偐側傝偺帺桼搙偱嬻傪旘傇偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丄擔杮偵偼傾儊儕僇偺傛偆側僄僋僗儁儕儊儞僞儖丒僇僥僑儕乕偼側偔丄儂乕儉價儖僩婡傪旘峴偝偣傞応崌偼丄巊梡旘峴応丄
旘峴崅搙丄旘峴斖埻側偳偐側傝嵶偐偔惂栺偝傟偨忋偱偺傒嫋壜偝傟傞丅偙傟偼丄抧忋傗旘峴偺埨慡偵廫暘攝椂偟偨寢壥偩偲峫偊傜傟傞偑丄尒曽傪曄偊
傞偲丄愴屻擔杮偺帺嶌峲嬻婡暥壔偑朢偟偔惢嶌傕傎偲傫偳峴傢傟側偐偭偨偨傔丄傾儊儕僇偺傛偆側僇僥僑儕乕偑惗傑傟偰偔傞娐嫬偑堢偭偰偙側偐偭偨
偺偱偼側偄偩傠偆偐丅梫偡傞偵丄偄偔傜傾儊儕僇偱侾侽侽侽婡埲忋偺斕攧幚愌傪屩傝丄傾儊儕僇偱偼僙僗僫傗僷僀僷乕側偳偺儊乕僇乕婡偲摨偠傛偆偵嬻傪旘傫偱偄傞儂乕儉 價儖僩婡偱偁偭偰傕丄偟偐傕旘峴婡偺僾儘偨偪偑乮偨偲偊慡堳偑惢嶌偺僾儘偱偼側偄偵偟偰傕乯旘峴婡偺僾儘偲偟偰抪偢偐偟偔側偄傛偆偵嶌偭偨傕偺 偱偁偭偨偲偟偰傕丄擔杮偱偼応廃旘峴偟偐擣傔傜傟側偄壜擻惈偑崅偄偺偩丅
丂偟偐偟乽俵俙俠俫 俛仌俥乿偺儊儞僶乕偺懡偔偼丄乽儊乕僇乕婡乿傪帺暘偨偪偺庤偱嶌偭偰偄傞丅惉憌寳偺斵曽偱崙杊偺擟偵偮偒丄偁傞偄偼悢昐柤 傕偺忔媞傪忔偣偰嬻傪旘傇旘峴婡傪嶌偭偰偄傞偺偲摨偠恖娫偑丄摨偠傛偆側拲堄傪暐偭偰嶌偭偨旘峴婡側偺偵丄偳偆偟偰旘峴応廃曈偟偐旘傋側偄棟桼 偑偁傞偩傠偆偐丅
乽巹偨偪傕嵟弶偼柍棟偩偲巚偭偰偄傑偟偨丅偱傕丄偄傑偼杮婥偱擔杮拞偺嬻傪旘傫偱傒偨偄偲峫偊偰偄傑偡乿
偦偆偩丄旘傋側偄棟桼偼側偄丅
彨棃偼僆儕僕僫儖丒儂乕儉價儖僩婡傪
俼倁亅俇俙偼偦偺戞堦曕偵偡偓側偄
 丂乽俵俙俠俫 俛仌俥乿偺俼倁亅俇俙偼丄慺恖栚偵偼儊乕僇乕婡偲傑傞偱懟怓偑側偄傛偆偵嶌傜傟偰偄傞丅儂乕儉價儖僩婡偱偙偙傑偱嬅傞偐側偲巚偆傛偆側嶌傝偩丅僄儞僕儞偩偭偰丄拞屆側偑傜僆乕僶乕儂乕儖偝傟偰懴嬻惈傕彂椶傕偟偭偐傝偟偨峲嬻梡傪憰旛偡傞梊掕偱偁傞丅儂乕儉價儖僩婡側傜偽帺摦幵梡僄儞僕儞傪憰旛偡傞偙偲傕捒偟偔側偄偟丄峲嬻梡偱傕慺惈偺夦偟偄僄儞僕儞側傜偽偄偔傜偱傕埨偔庤偵擖傞丅偟偐偟丄偦傟偱偼峲嬻嬊傪愢摼偡傞偙偲偼傓偢偐偟偄丅偩偐傜偁偔傑偱乽杮暔乿偵偙偩傢傞丅
丂乽俵俙俠俫 俛仌俥乿偺俼倁亅俇俙偼丄慺恖栚偵偼儊乕僇乕婡偲傑傞偱懟怓偑側偄傛偆偵嶌傜傟偰偄傞丅儂乕儉價儖僩婡偱偙偙傑偱嬅傞偐側偲巚偆傛偆側嶌傝偩丅僄儞僕儞偩偭偰丄拞屆側偑傜僆乕僶乕儂乕儖偝傟偰懴嬻惈傕彂椶傕偟偭偐傝偟偨峲嬻梡傪憰旛偡傞梊掕偱偁傞丅儂乕儉價儖僩婡側傜偽帺摦幵梡僄儞僕儞傪憰旛偡傞偙偲傕捒偟偔側偄偟丄峲嬻梡偱傕慺惈偺夦偟偄僄儞僕儞側傜偽偄偔傜偱傕埨偔庤偵擖傞丅偟偐偟丄偦傟偱偼峲嬻嬊傪愢摼偡傞偙偲偼傓偢偐偟偄丅偩偐傜偁偔傑偱乽杮暔乿偵偙偩傢傞丅丂偙傟偼偲傫偱傕側偄偙偲偵側偭偰偒偨側偲巚偭偨偑丄儂乕儉價儖僩婡偱擔杮拞傪旘傇偙偲偑乽俵俙俠俫 俛仌俥乿偺嵟廔栚昗偱偼側偄偲暦偄偰偝傜 偵嬃偄偰偟傑偭偨丅
乽偣偭偐偔偙傟偩偗偺儊儞僶乕偑偦傠偭偨偺偱偡偐傜丄傗偼傝愝寁偐傜僆儕僕僫儖偺儂乕儉價儖僩婡傪嶌偭偰旘偽偟偨偄偠傖側偄偱偡偐丅傕偪傠傫嵟 弶偐傜偦傫側偙偲傪偄偭偰傕恎偺掱抦傜偢偱偟傚偆丅偱偡偐傜俼倁亅俇俙傪庤巒傔偵懠偺僉僢僩側偳傕惢嶌偟偰宱尡偲幚愌傪愊傫偩偆偊偱偺丄彨棃偺 栚昗偲峫偊偰偄傑偡乿
丂側傫偰慺惏傜偟偄榖側偺偩傠偆丅愳嶈廳岺傗嶰旽廳岺側偳擔杮傪戙昞偡傞儊乕僇乕偺恖偨偪偑拞怱偲側偭偰丄儃儔儞僥傿傾偱僆儕僕僫儖婡傪愝寁偟丄 惢嶌偟丄旘偽偡丅傂傚偭偲偟偨傜僶乕僩丒儖乕僞儞偝偊嬃偐偡偙偲偑偱偒傞傛偆側儐僯乕僋側婡懱偑惗傑傟傞偐傕偟傟側偄丅
 丂偙偆偟偨柌傪幚尰偡傞偨傔偵傕丄儂乕儉價儖僩婡偱擔杮慡崙傪旘傇偲偄偆寁夋偼偤傂幚尰偟側偗傟偽側傜側偄丅偨偩旘偽偡偩偗側傜偽丄擔杮偑懯栚
偱傕傾儊儕僇偵帩偪崬傫偱俶僫儞僶乕偱搊榐偡傞偲偄偆曽朄傕偁傞偩傠偆丅偟偐偟偦傟偱偼丄偣偭偐偔偺惗傑傟傛偆偲偡傞擔杮僆儕僕僫儖丒儂乕儉價
儖僩婡偺枹棃偺夎傪揈傒庢偭偰偟傑偆偙偲偵側傝偐偹側偄丅
丂偙偆偟偨柌傪幚尰偡傞偨傔偵傕丄儂乕儉價儖僩婡偱擔杮慡崙傪旘傇偲偄偆寁夋偼偤傂幚尰偟側偗傟偽側傜側偄丅偨偩旘偽偡偩偗側傜偽丄擔杮偑懯栚
偱傕傾儊儕僇偵帩偪崬傫偱俶僫儞僶乕偱搊榐偡傞偲偄偆曽朄傕偁傞偩傠偆丅偟偐偟偦傟偱偼丄偣偭偐偔偺惗傑傟傛偆偲偡傞擔杮僆儕僕僫儖丒儂乕儉價
儖僩婡偺枹棃偺夎傪揈傒庢偭偰偟傑偆偙偲偵側傝偐偹側偄丅丂偦傕偦傕儂乕儉價儖僩婡傪嶌傠偆偲偄偆寁夋偼丄擔杮偺峲嬻塅拡嶻嬈偺拞怱抧偱偁傞拞晹抧曽偺峲嬻嶻嬈傪怳嫽偟傛偆偲偄偆抍懱傗峴惌偑丄堦斒偺 恖偵傕旘峴婡偵偮偄偰偺抦幆傗棟夝傪怺傔偰傕傜偍偆偲僗僞乕僩偟偨傕偺偩丅偟偐偟偦偺寢枛偑丄乽旘峴婡偼偱偒偰傕擔杮偱偼儘僋偵旘偽偣側偄偲偄 偆偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅偦傟偑擔杮偺峲嬻奅偺尰忬偱偡乿偲偄偆偺偱偼丄柌傕婓朷傕側偄丅
丂旘峴婡傪嶌偭偰乽旘偽偡乿偲偄偆乽俵俙俠俫 俛仌俥乿偺挧愴偼丄偙傟偐傜偑惓擮応偲偄偊傞丅
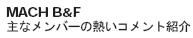 彫嶳悷恖偝傫 丂埲慜偐傜攷暔娰偺儃儔儞僥傿傾傕柋傔偰偍傝丄儗僗僩傾偵嫽枴偑偁傝傑偟偨丅峲嬻婡儊乕僇乕偱惗嶻媄弍娭楢偺巇帠傪偟偰偄傞偺偱偡偑丄巇帠偱儕儀僢僩傪懪偮婡夛偲偄偆偺偼偁傝傑偣傫丅幚嵺偵帺暘偱嶌偭偰傒傞偙偲偱丄曌嫮偵側傝傑偡偹丅 堜忋彯偝傫 丂妛惗帪戙偐傜僌儔僀僟乕偺憖廲偲惍旛偺宱尡偼偁傝傑偟偨偐傜丄崱搙偼旘峴婡傪嶌偭偰旘偽偡偺傕偄偄側偁偲丅偙傟傑偱乽杮嬈乿偺偍媞偝傫偐傜乽偙偙偑嶌嬈偟偢傜偄乿偲偄傢傟偰傕僺儞偲偙側偄偙偲偑偁偭偨偺偱偡偑丄偄傑偼帺暘偱偝傫偞傫嬯楯偟偰乽側傞傎偳乿偲丅曌嫮偵側傝傑偡 桍悾暥徍偝傫 丂扤傕偑婥寉偵椃媞婡傪棙梡偡傞帪戙偱偡偑丄偦偺巇慻傒傪抦偭偰偄傞恖偼偁傑傝偄側偄丅偱傕丄偁傫側偵戝偒側傕偺傪旘偽偡媄弍偲偄偆偺偼慺惏傜偟偄偲巚偆傫偱偡傛丅傑偨偦偆偟偨媄弍傪攟偭偰偒偨暥壔偲偄偆傕偺傕偁傞丅偦偆偟偨偙偲偵嫽枴傪傕偭偰偔傟傞恖偑彮偟偱傕憹偊偰偔傟傟偽偄偄側偲巚偭偰偄傑偡丅 |
壛摗梲巕丄媑塱廏恖丄曅嶳攷暥偝傫 丂傒側杮嬈偱偼僐儞僺儏乕僞偱旘峴婡傪旘偽偡傛偆側巇帠傪偟偰偄傑偡偑丄偁傑傝乽幚婡乿偵偝傢傞婡夛偼側偄傫偱偡丅乽偦傟偠傖偄偐傫乿偲桿傢傟傑偟偨丅僐儞僺儏乕僞傕偄偄偱偡偑丄巕嫙偨偪偵巻僸僐乕僉偲偐嫵偊偰偁偘偨偄偱偡偹丅 崟桍復偝傫 丂帺暘偨偪偱嶌偭偰旘偽偣傞側傜柺敀偄偲巚偭偰嶲壛偟傑偟偨丅旘傫偩傜嵟崅偵姶寖偡傞偱偟傚偆偹丅 堷抧桼婭偝傫 丂埨懞偝傫偵乽庁傝乿偑偁偭偰嶲壛偟傑偟偨偑丄崱偼帺庡揑偵妝偟傫偱偄傑偡丅僇僢僷偺堖憰偼埨懞偝傫偵拝偰偙偄偲偄傢傟偨傢偗偠傖偁傝傑偣傫乧丄杮摉偱偡丅 嫶杮抦巕偝傫 丂儈僔儞偑巊偊傞偺偱偤傂嶲壛偟偰傎偟偄偲棅傑傟傑偟偨丅嵟弶偵嶌偭偨偺偼旘峴婡偱偼側偔儚僢儁儞偱偟偨偗偳丅 娸杮徆暥偝傫 丂旘偽偡偺偑杮嬈側傫偱偡偑丄搉绯偝傫偐傜乽僸儅偩傠偆丅棃偄乿偲丅杮恖傪慜偵偟偰偄傞偐傜偠傖側偄偱偡偑丄柺敀偄偱偡丅偙偙偼偙偆側偭偰偄偨偺偐偭偰丄曌嫮偵側傝傑偡丅偲傝偁偊偢僼儔僀僩偼搉绯偝傫傗埨懞偝傫偵偍傑偐偣偟傛偆偲巚偭偰偄傑偡丅偄傗丄帺暘偱嶌偭偨傕偺偵帺怣偑側偄傢偗偠傖側偄傫偱偡偑乧丅 |
幨恀偲暥 垻巤岝撿
幨恀採嫙 俵俙俠俫 俛仌俥
庢嵽嫤椡 偐偐傒偑偼傜峲嬻塅拡壢妛攷暔娰
俶俹俷朄恖乮摿掕旕塩棙妶摦朄恖乯俵俙俠俫 俛仌俥
仹509-0115丂婒晫導奺柋尨巗椢墤撿俁挌栚俉俇斣抧
揹榖斣崋乛俥俙倃 丂050-3407-3013
http://www.machbaf.org/
幨恀採嫙 俵俙俠俫 俛仌俥
庢嵽嫤椡 偐偐傒偑偼傜峲嬻塅拡壢妛攷暔娰
俶俹俷朄恖乮摿掕旕塩棙妶摦朄恖乯俵俙俠俫 俛仌俥
仹509-0115丂婒晫導奺柋尨巗椢墤撿俁挌栚俉俇斣抧
揹榖斣崋乛俥俙倃 丂050-3407-3013
http://www.machbaf.org/